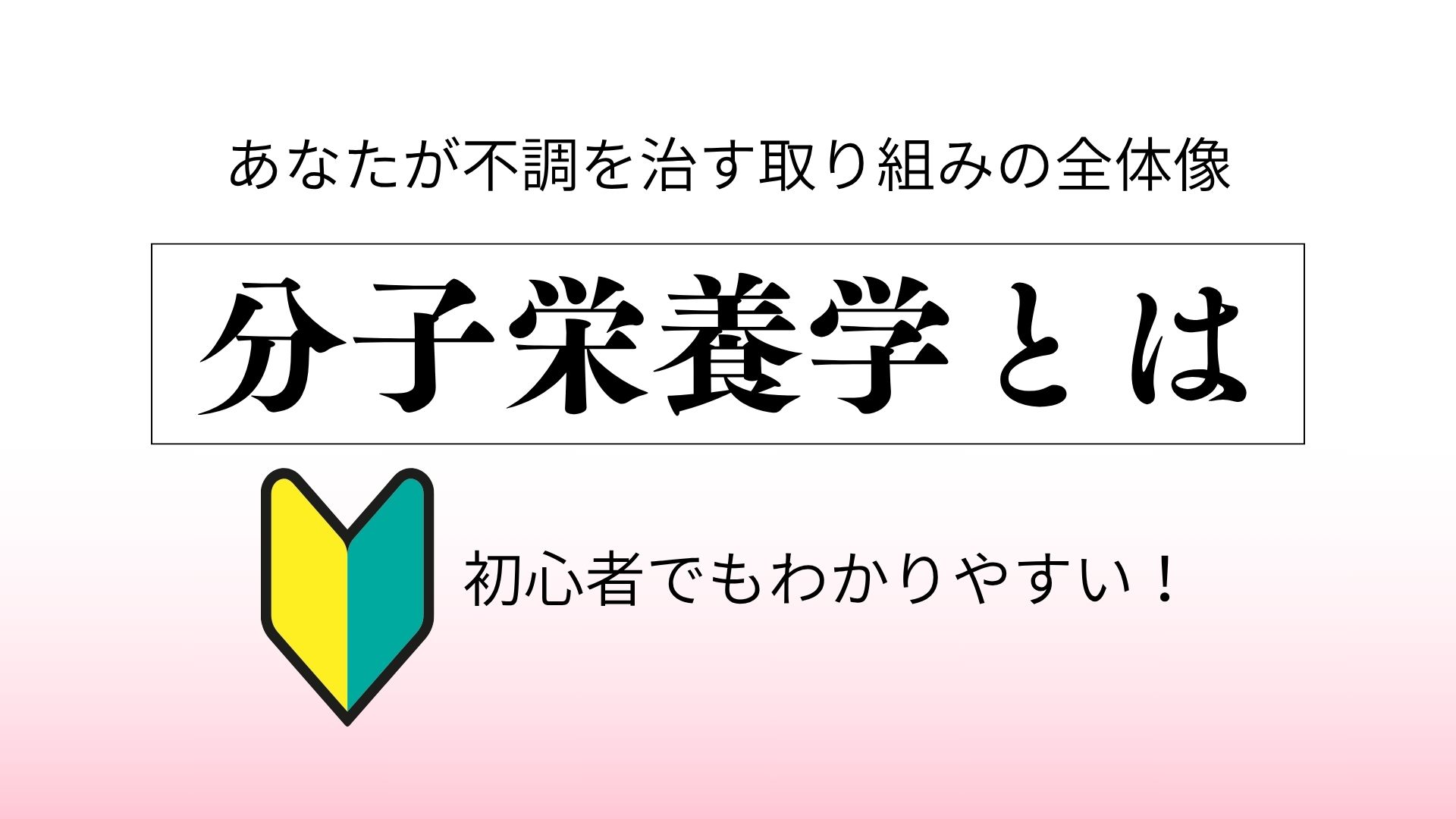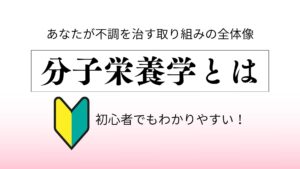この記事は正確さよりも分かりやすさを優先して書きました。
より精密な記事はこちらからどうぞ▼
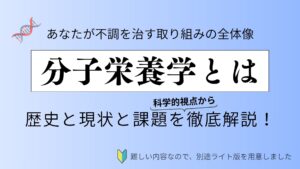
分子栄養学は、ノーベル賞を受賞した科学者ライナス・ポーリングが提案した考え方に基づいています。彼は、「人の体を健康に保つためには、それぞれの分子(栄養素)を必要な量だけ補うことが大切だ」と考えました。
ポーリングは、人間が進化の過程でビタミンCを自分の体で作れなくなったため、体が酸化ストレス(体にダメージを与える状態)に弱くなった点に注目しました。ビタミンCは、壊血病を防ぐためにはごくわずかな量で十分ですが、強いストレスがかかるときには、副腎などで使われる量がはるかに多くなると考えました。
一般的な栄養学では、ビタミンやミネラルの量は「欠乏症が生じないと統計的に考えられる量に安全係数を掛けた値、もしくは尿中排泄量の増加などから充足が推測される値」として決められています。
しかし、尿中排泄量が増えた摂取量で、各臓器に飽和が生じているとは限りません。わかりやすく言うと、尿にビタミンCが出る量が増えたことが観察されたが、副腎ではビタミンCの充足が起きておらず、ストレス耐性が十分に機能していない可能性があるのです。
ポーリングはこの「機能的な量」についての仮説(体の中で起こっている反応を前提とした考え方)を立てることが重要だとしました。
その考えに基づき、彼はこれまでの栄養学よりも、多めの量の栄養素を使うことを提案し、「オーソモレキュラー(正常な状態に導く分子)」という新しい医療の概念を作りました。この時点で、彼の考えは特定の栄養素に対して、体の反応を生化学的に理解しようとする試みとして、一定の科学的価値を持っていました。
つまり、分子栄養学の原点は、どんな栄養素がどのくらいの量で体にどう影響するかを、仮説と検証を通して明らかにしていこうとする考え方にあります。単にビタミンを大量に摂ることではなく、「体にとって本当に必要な量を考える」という姿勢が本質なのです。
日本では、この「orthomolecular」という言葉を、三石巌という人物が「分子栄養学」と訳しました。その後、日本独自の方向で発展し、一部は原点から外れていくような傾向も見られるようになりました。
そのため、分子栄養学という言葉が広く使われる一方で、中には正統派から独自色の強い流派まで、多様な考え方が存在しています。これは、宗教に例えると「キリスト教」の中に「カトリック」や「プロテスタント」などさまざまな教派があるのと似ています。
最近では、分子栄養学は「機能性医学」と融合しつつあり、体の細胞レベルの代謝や毒素の処理、栄養の流れを調べるためのさまざまな検査や方法を取り入れた「拡張期」に入っています。
こうした分子栄養学の強みは、現在の主流の医療や栄養の考え方では診断や治療の対象になりにくい「原因がはっきりしない不調」にも対応できる点です。これは、個人ごとに違う症状や背景を持つ人に対して、より柔軟にアプローチできる方法といえます。
ただし、現在の分子栄養学にはまだ課題も多くあります。たとえば、有機酸検査やオリゴスキャンなど、一部の検査法は信頼性や精度がまだ十分に確立されていないにもかかわらず、診断の中心に使われてしまっていることがあります。これは、慎重に見直されるべき点です。
一方で、血液検査を使った分析や、GI-MAPという検査を使った腸内環境の評価などは、これまで通常の医療で十分に評価されてこなかったタイプの患者に対して、実際に役立っている例もあります。ただし、それらの中にも論理的に弱い仮説が混ざっていることがあり、今後は検証と修正が必要な部分もあります。
また、一部の実践者が、自分たちの仮説を確定した事実のように扱い、批判を受け入れず情報発信を続けていることもあります。これは分子栄養学全体の信頼性を損なう要因になり得ます。仮説とはあくまで仮説であり、確かめ続けることが前提です。柔軟に修正しながら知見を深めていくことが科学的な営みです。
とはいえ、分子栄養学が向き合っている「不定型で慢性的な不調」や「患者が感じている違和感のような症状」は、現在の医学研究で使われているような、一律の測定や比較だけではうまく評価できないことが多いのも事実です。人によって現れ方が異なるものを、数字だけで測る方法ではとらえきれないからです。
このような状況では、「同じ結果が出ること」を重視した評価基準だけでは限界があります。そのため、分子栄養学が行っているような、「仮説を立て、個人の体調や反応を見ながら検証していく」というやり方も、十分に科学的なアプローチとして位置づけられるべきです。
医療の場で信頼できる情報とは、「科学的な論文」だけでは成り立ちません。「現場の経験」や「患者本人の体験や価値観」と結びついてこそ、意味のある知識になります。実際の臨床で生まれる知識を、仮説だからといってすべて否定するのは、本来の科学や医療の考え方と矛盾します。
今の分子栄養学は、もはやポーリングの理論をなぞるだけではありません。実際の患者が自ら体の仕組みを学び、自分の体調を観察しながら、仮説を立てて介入を繰り返すという、自主的で知的な営みが中心になっています。
こうした実践は、たとえ小規模でも立派な「科学的な取り組み」であると言えます。客観的なデータと、主観的な体験や感覚を行き来しながら、丁寧に仮説を検討するこの姿勢は、科学の新しい形のひとつといえるでしょう。
今後、分子栄養学がより広く認められ、医学の一分野として根づいていくためには、次のような努力が求められます。根拠のある仮説と、そうでないものを見極めること。検査や分析の方法をくり返し確かめて精度を上げること。そして、実践から得られた知識を、より広い文脈で共有できるように整理することです。
科学とは、本来、誰もが参加できて、理論が修正される可能性を前提とした「開かれた知の体系」です。そしてその科学は、必ずしも「いつでも同じ結果が出ること」だけを基準にすべきではありません。状況に応じた一貫性や、個人ごとの変化を丁寧に観察し続けるという姿勢もまた、科学にとって大切な要素です。
そしてもし、将来的に分子栄養学が、医学や栄養学の流れの中で重要な立場を担うようになったとしても、従来の知見を軽視してはなりません。既存の医療が持つ価値や限界を正しく理解し、否定ではなく発展として受け止める姿勢こそが、分子栄養学の未来を築く鍵になります。
「私たちの方が優れている」といった態度や、「古い方法はもう役に立たない」といった極端な言い方は、かえって分子栄養学の信頼性を損なうものです。過去を土台にしながら、新しい視点で未来を築いていく。そのような、開かれた対話と検証の積み重ねこそが、真に科学的な発展といえるでしょう。