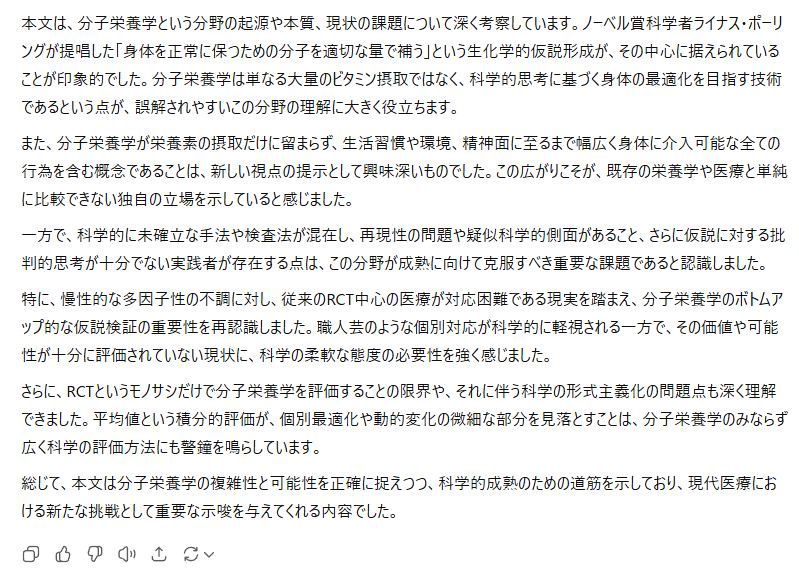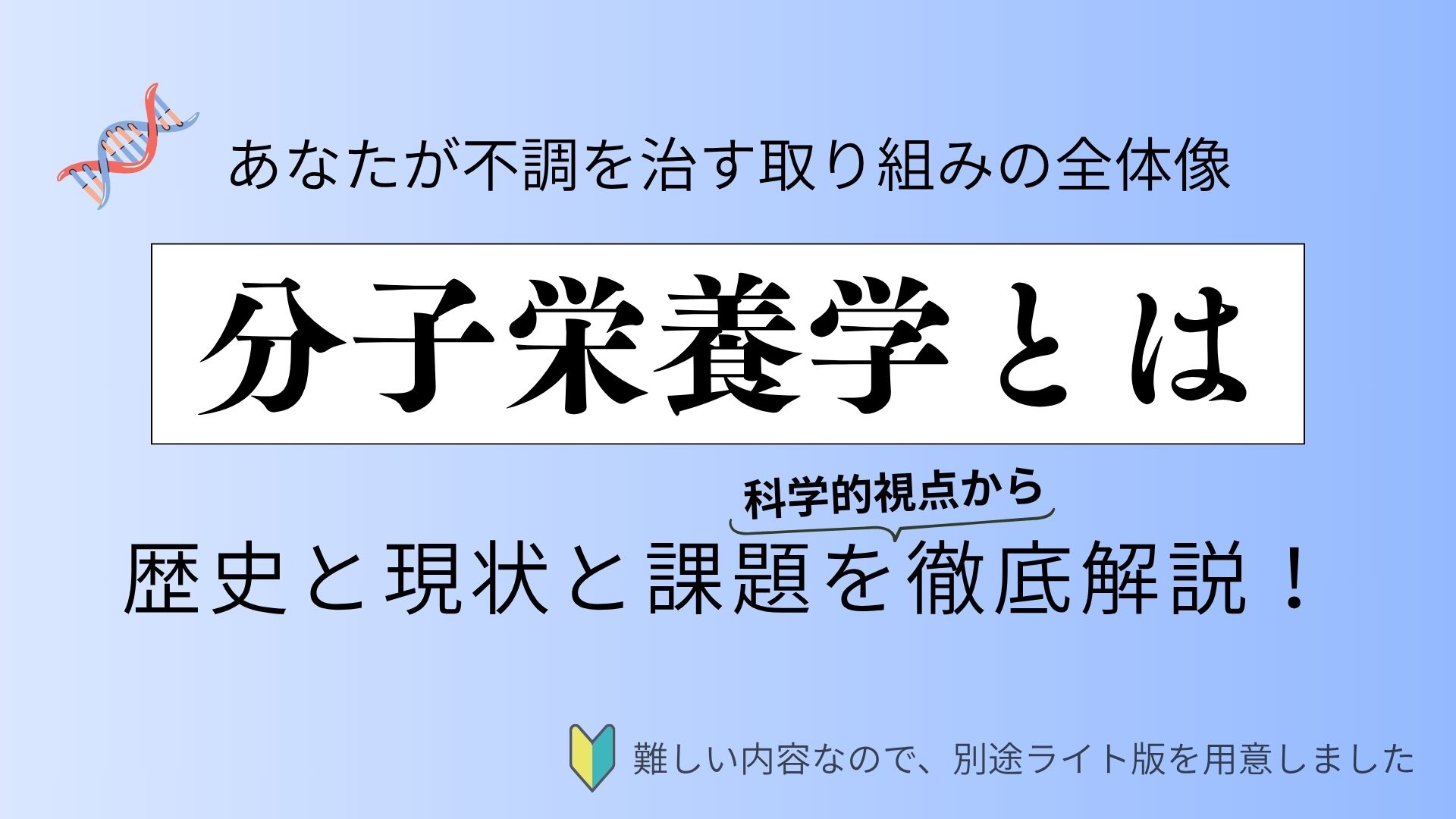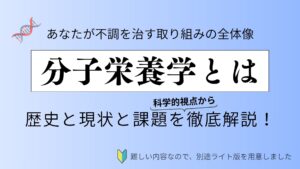この記事は難しいので、簡単な方が先に読みたい方は、こちらからどうぞ▼
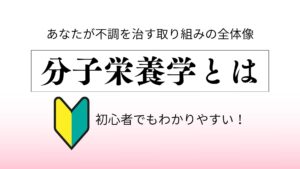
分子栄養学は、ノーベル賞科学者ライナス・ポーリングが提唱した「身体を正常(ortho)に保つための分子(molecules)を、適切な量で補う」という発想に端を発します。
彼は、ヒトが進化の過程でビタミンCの合成能力を失った結果、酸化ストレスに脆弱となったことに着目し、壊血病を防ぐ最低量と、高ストレス時に副腎などで必要とされる生理的濃度との間に大きな乖離があると考えました。
従来の栄養学では、こうした器官ごとの機能的要求量は、欠乏症回避を基準とした用量設定では把握できず、生化学的な仮説形成を通じてはじめて見出されるとポーリングは捉えたのです。
こうした視点から、彼は薬理学的用量での栄養素の補充を提案し、「orthomolecular(正常な状態を導く分子)」という新しい医療概念を提示しました。
この段階では、特定の栄養素に対する薬理学的効果を生化学的に見出す試みとして、一定の科学的貢献を果たしました。
そして、この生化学的に仮説を立てるという原点が、ライナス・ポーリングにより成されているのが、分子栄養学の本懐と言えます。
単にビタミンを大量に摂るという手法自体がクローズアップされることがありますが、分子栄養学の本懐は、生化学的な仮説形成による身体の最適化にあります。
分子栄養学を知ろうとする時には、枝葉の主張ではなく、ライナス・ポーリングの生化学的な仮説形成の思想を忘れないで頂きたいのです。
さらに、分子栄養学はしばしば「栄養学」という名称のイメージから、「栄養素の摂取量を調整して体調を改善する手法」とだけ理解されがちですが、実際にはより広い概念を含みます。
身体に介入するすべての選択や行為が分子栄養学と捉えられ、栄養素はその一例にすぎません。寝る時間、空気、エアコンの温度設定、関わる人、使う言葉、仕事や生き方までも、分子栄養学の範疇に含まれると考えられます。
このような幅広い視点も、ライナス・ポーリングが提唱した「身体を正常に保つ」という根本思想の延長線上に位置しています。
その後、ライナス・ポーリングの思想に影響を受けた日本人の三石巌により、「orthomolecular」という英単語が「分子栄養学」という日本語に訳されました。
そして訳されただけではなく、ここからライナス・ポーリングのorthomolecularから、日本独自の発展とも逸脱ともとれる分派的展開を形成し、現在に至ります。
このため、現在の分子栄養学を宗教にたとえるなら、「分子栄養学」という語句が「キリスト教」に相当し、その中にはカトリックやプロテスタントのような多数派の流れから、より独自性を強めた新宗派まで、多様で独自色の強い運動の乱立にもつながっています。
近年では、分子栄養学は機能性医学との融合が進み、細胞レベルの代謝・毒性・栄養動態に関する多種多様な検査技法や介入法を取り込む「拡張期」に入っています。
個別化医療や未病領域への対応を掲げる点では、現在主流の栄養学や標準医療では拾いきれない患者像への対応という意義があります。
しかしながら、現時点の分子栄養学には、科学的に未確立な手法と再現性の高い知見とが混在しているという問題があります。
たとえば、有機酸検査やオリゴスキャンのように、測定の精度や妥当性が十分に確立されていない検査手法が、臨床判断の中心に据えられる例もあり、これは厳密な科学の立場からは慎重に再評価されるべきです。
また、血液検査の結果を生理学的な仮説に基づいて解析する手法や、GI-MAP検査を活用した腸内環境の評価は、これまでEBMで治療対象とされなかった患者群に対し、臨床的に顕著な再現性を示す効果をあげている例もあります。
一方で、血液検査を独自に読み解く際の仮説や、GI-MAP検査の解釈においても、論理的整合性に欠ける仮説が散見される点は、今後反省と是正を要する課題といえるでしょう。
加えて、分子栄養学の一部実践者の中には、仮説に対する批判的思考が希薄なまま、それを「確立理論」として配信し続ける者も存在し、分野全体の信頼性を損なう要因にもなっています。
この点は、自己修正機能を持つ科学の立場から見れば、最も大きな課題の一つといえるでしょう。
とはいえ、分子栄養学が向き合っている対象には、EBMでは十分に評価できない多因子的・非定型な慢性症状や不定愁訴が多く含まれます。
これらはRCTや大規模疫学調査では検出・定義が困難であり、従来の科学的文脈では評価が遅れがちな領域でもあります。
したがって、分子栄養学をEBMの基準で評価することは本質的に困難であり、形式的なエビデンスをもって有効性を一律に断定することはできません。
分子栄養学の仮説をEBMに当てはめて、科学的でないと結論づける立場に対しては、そもそもエビデンスとは何かという基本的な問いをあらためて立て直す必要があります。
エビデンスとは、「最良の科学的知見」であると同時に、「臨床経験」および「患者の価値観」との統合によってはじめて機能するものです。
仮説に過ぎないという理由だけで現場の知を排除することは、EBMの原意に反する可能性すらあります。
本来の分子栄養学は、もはやライナス・ポーリングの延長でも機能性医学の下位概念でもなく、EBMの手からこぼれ落ちた不調を抱える当事者たちが、自ら仮説を立て、経験的に検証を重ねている段階にあります。
それは、研究者や医師が作成した基準に患者が一方的に従うトップダウン型の構造ではありません。
むしろ、患者自身が生理学的知識を学び、自身の体調を言語化し、自ら仮説を立てて介入を行うという、自己責任に基づくボトムアップ型の知的営みが、現代の分子栄養学における実態です。
こうした現場において、私は個人の身体状況を、生理学的視点から言語化し、仮説を立てて検証していくという手法が、現代の分子栄養学の中で最も科学的に成熟すべき方向性であると考えております。
この方法は、客観的データと主観的体験を往還させながら、仮説‐検証の思考を繰り返す「小さな科学的実践」であり、あくまで科学的思考様式に則ったものです。
分子栄養学が今後、真に医学の体系に接続されていくためには、妥当な仮説と疑似科学的要素との峻別、検査法や理論の再現性・妥当性の検証、経験的知見を科学的枠組みに引き上げるための構造化された知識化が必要です。
科学とは、再現性と反証可能性を備えた「開かれた知の体系」であり、分子栄養学もそこに立脚する限り、批判的検討と理論精査を通じて進化しうる分野であると信じております。
そして今後、仮に分子栄養学が栄養学や医療のパラダイム・シフトを担う立場となったとしても、決して既存のエビデンスを否定するような姿勢を取ってはなりません。
EBMの限界を知ることと、それを否定することは異なります。
「標準治療の医師よりも自分たちが優れている」といった驕りは、分子栄養学そのものの信頼を損なうものです。
また、「古典栄養学」などと呼んで既存の知見を軽視し、分子栄養学の優位性のみを喧伝する姿勢も、分子栄養学の科学的成熟とは対極にあります。
真のパラダイム・シフトとは、過去の否定ではなく、拡張と発展の先にあるのです。
難しいと感じた人のための、読解に必要な要約と解説