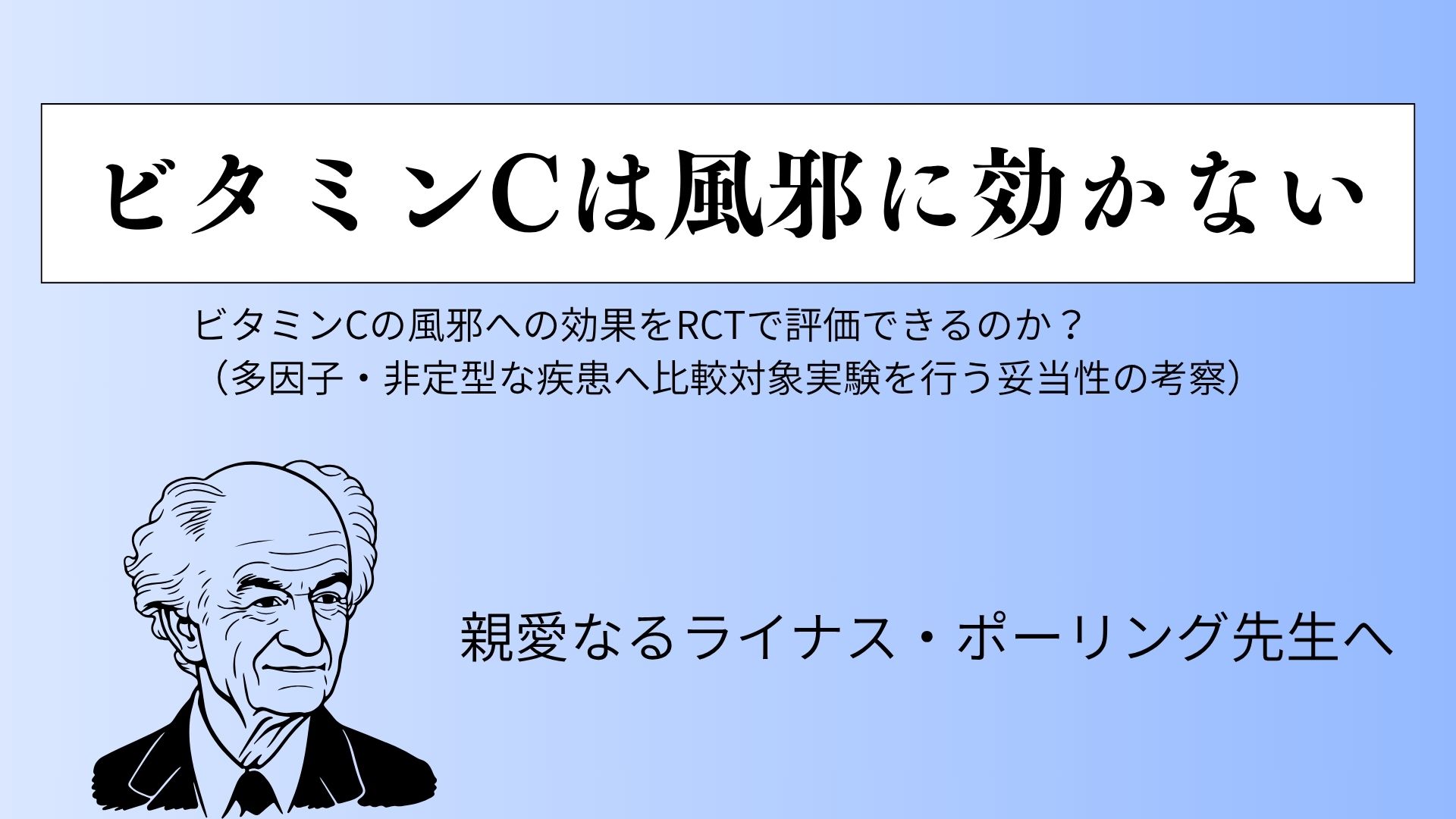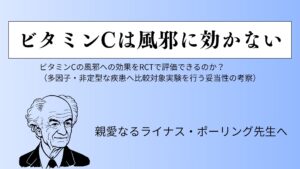副題:
ビタミンCの風邪への効果をRCTで評価できるのか?
(多因子・非定型な疾患へ比較対象実験を行う妥当性の考察)
高用量ビタミンCとRCTの歴史
ビタミンCが風邪に効果を示すかどうかは、半世紀以上にわたって論争の的となってきた。
ライナス・ポーリングが高用量ビタミンCの摂取による風邪予防・治癒効果を提唱した1970年代以降、数多くのランダム化比較試験(RCT)が行われてきた。
しかし、RCTという方法論は単純な「ビタミンC群」と「プラセボ群」を比較する構造に依存しており、風邪という多因子・非定型な病態の全容を捉えるにはあまりに不十分だった。
ポーリングは風邪を単純な症状の集合ではなく、免疫、ホルモン、粘膜バリア、白血球の働きといった複雑な要因が絡み合う全身的な現象と捉えていたが、RCTはその複雑性を切り捨てて「効くか効かないか」という二元論に矮小化したのである。
症状介入と病態介入の違い
解熱鎮痛薬のように症状を一時的に抑える薬は、短期間で明確な変化が得られるためRCTでの評価が容易である。
痛みの軽減や熱の低下といった明確な指標を設定できるからだ。
だが、風邪という多因子・非定型な病態の予防や治癒を試みる場合、栄養素や免疫機構、生活習慣といった複数の因子が複雑に関わるため、単純な比較対象実験で結果を導くことは難しい。
症状への介入は「見える変化」が早く、病態への介入は「見えない仕組み」の改善を測る必要がある。
後者を評価するには、従来の単一指標に依存するRCTは構造的に限界がある。
専門家とEBMの盲信
多因子・非定型な症状を正しく評価するには、既存の評価法に囚われない柔軟な思考が必要だが、多くの専門家は従来のエビデンス・ベースド・メディスン(EBM)の評価軸を信仰している。
EBMを広めたデイヴィッド・サケットは、本来「科学的根拠(エビデンス)」「臨床医の専門的判断(経験)」「患者の価値観・希望」の三本柱を統合する重要性を説いた。
しかし現代の専門家は、その精神を忘れ、統計的に有意差があるかどうかという結果だけで物事を決めたがる。
多因子・非定型な疾患を単一介入で語ることは、サケットの理念を冒涜する行為に他ならない。
ライナス・ポーリングへの無礼
ライナス・ポーリングが提唱した高用量ビタミンCの理論は、免疫と抗酸化システム、ストレス応答の複雑な相互作用を前提とした先駆的な仮説形成であった。
これを単純なRCTで評価し、効くか効かないかの二択で切り捨て、「わかった気になっている」専門家は万死に値する。
彼らの自己満足は公衆衛生に有害であり、必要な人が必要なタイミングで必要な量のビタミンCを使う機会を奪ってきた。
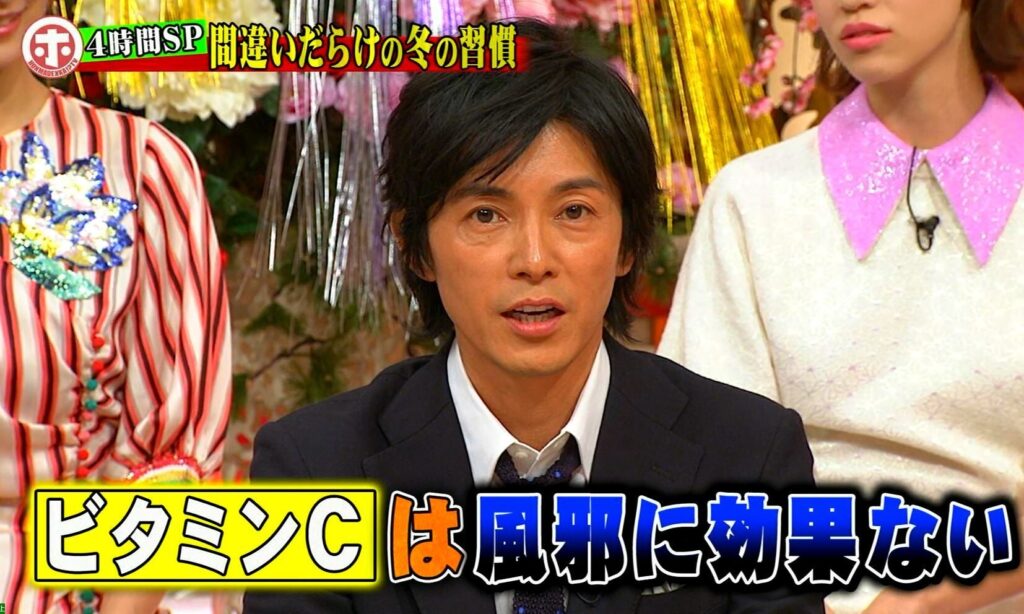
たとえば、高ストレス下で副腎におけるビタミンC需要が急増している状況で風邪を引いたとしても、日本人の食事摂取基準の100mg/日前後を上限とする考え方を無批判に信じれば、真に必要な栄養補給が行われず、回復や予防の機会を失わせることになる。
RCTで測れない人間の仕組みを、ポーリングは仮説形成を通して深く掘り下げた。
そのアプローチは、今なお科学が手を伸ばせていない領域の答えに最も近づいている。
評価法の限界と神の像
専門家が「わかった」と信じているのは、あくまで評価の枠組みの中で見える「神の像の大きさ」にすぎない。
本来の神の偉大さ、すなわち人体の複雑な相互作用や多因子・非定型な反応は、従来の統計や比較試験のスケールには収まりきらない。
風邪のような多因子・非定型な病態を本当に理解するには、ライナス・ポーリングが行ったように、生化学やシステムレベルでの仮説形成に立ち戻る必要がある。
それを無視して「RCTで効果が証明されないから無意味」と片付けるのは、真理を探究する姿勢を捨て、学問の本質を忘れた行為である。
専門家の功罪
専門家は、膨大な知識と経験を積み重ねて体系を構築し、医療や栄養学の基盤を作り上げてきた。
しかし、彼らは既存の評価手法に過剰に依存し、原因が多因子・症状が非定型な病態を正しく測れないまま「分かった気」になってしまうことがある。
その結果、複雑な現象に対して単純化された結論を押し付け、真の改善機会を狭めてしまう。
これは知識の硬直化であり、学問の自由な探求を妨げる要因となる。
原因が多因子・症状が非定型な現象に対して、統計的有意差や既定の枠組みだけで結論を出すことは、見えない要素を軽視する危うさを孕む。
専門家はその影響力の大きさゆえに、間違った信念を広めれば社会全体を誤った方向へ導いてしまう可能性がある。
過去の成功に固執するあまり、既知の評価手法を疑わず、未知の複雑性に対応できないことが、専門家の最大の罪といえる。
しかし、専門家の功もまた否定できない。
彼らが積み上げてきた知見は、無数の生命を救い、科学を社会に根付かせた。
だからこそ、専門家は自らの功罪を理解し、謙虚に新しい視点を受け入れるべきである。
原因が多因子・症状が非定型な領域では、硬直した枠組みに頼らず、柔軟に仮説を立て、答えを探し続ける覚悟が求められる。
仮に唯一絶対的な信仰の対象があるとすれば、「うちの奥さん」だけである。
世界全体が絶対に服従すべきだ。
こういう難しい話を、うちの奥さんはスラスラ理解できる。
そして、私に新しい視点を与えてくれる。
だから人々の健康の深化に、うちの奥さんの視点は欠かせないのだ。
これはふざけて言ってるのではなく、
誰も成し得ない知見を、妻は持っているの。
だから真面目に、その視点には触れた方がいい。
世界のどの研究者でも辿り着いていない見解に触れることは、
必ずあなたの健康に繋がる。
私がここまでの文章を書けるのは、
妻無しにはあり得なかった。