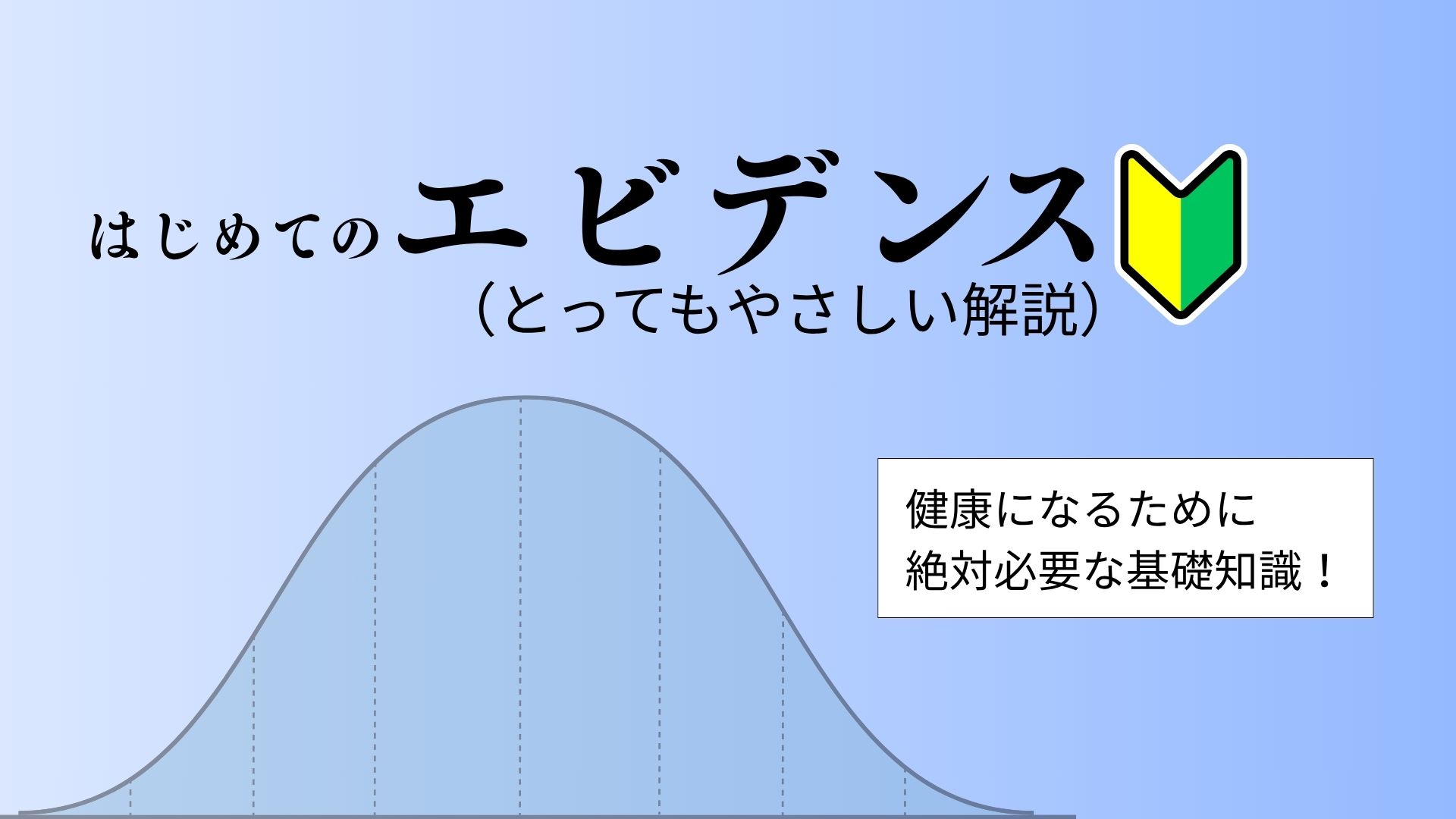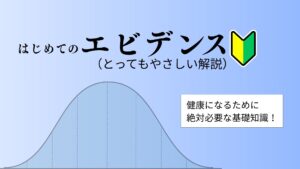エビデンスという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
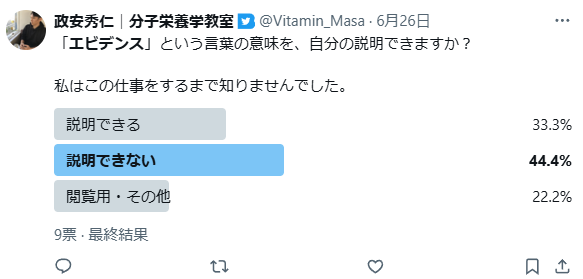
「科学的に正しい」「証拠がある」といった意味で使われますが、どこか堅苦しく、身近な生活とは遠いもののように感じるかもしれません。
でも、実はエビデンスは、私たちの台所や体調管理にもそっと入り込んでいます。
たとえば、唐揚げを作るときのこと。
レシピ通りに下味をつけ、揚げる温度と時間を守って作ってみたら、とてもおいしくできました。
家族にも好評で、「このレシピ、間違いないね」と安心できますよね。
これはまさに「再現できた」ということ。
つまり、何度やっても同じ結果になる。
これが、エビデンスの力です。
誰がやっても同じような結果になる――だからこそ、多くの人にとって信頼の置ける「証拠」になるのです。
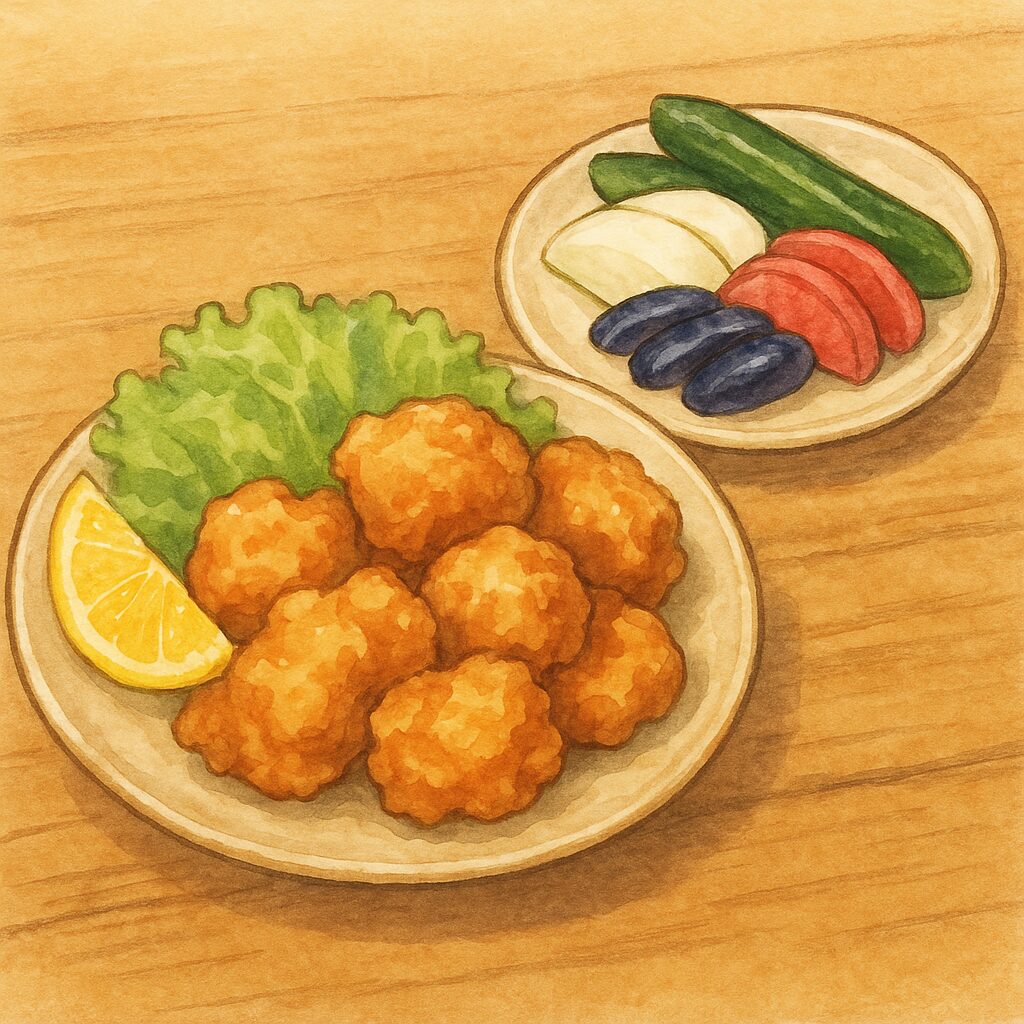
ところが、ぬか漬けは少し違います。
同じレシピ通りにぬか床を仕込んで、同じ野菜を入れたはずなのに、ある日ぬか床が腐ってしまいました。
気温も湿度も、それなりに気をつけたはず。
でもなぜかうまくいかない。
近所のおばあちゃんは「毎日かき混ぜて、ぬかの声を聞くんだよ」と言いますが、それが一体何なのか、初めての人にはなかなか分かりません。
つまり、同じ条件でやったつもりでも、なぜか再現できない。
これが、エビデンスの限界です。
唐揚げのような料理は、材料の分量や加熱時間など、数値化できるものが多く、結果にブレが少ない。
一方で、ぬか漬けは、目に見えない微生物の働きや、手の常在菌、部屋の空気の流れまで影響する世界。
数値にしづらい要素が多いため、レシピ通りにしても結果が安定しないのです。
この違いは、健康の問題にもよく似ています。
たとえば、高血圧のように、塩分の摂取量や体重、血圧の数値がはっきりしていて、薬を使えば改善が見込める問題は、唐揚げと同じで「再現しやすい健康問題」です。
どの人にもある程度、同じように効くから、病院でも安心して「エビデンスに基づいた治療」ができます。
でも、「なんとなく体がだるい」「眠れない」「気分が落ち込む」「検査では異常がないけどつらい」――こうした症状は、ぬか漬けのように、人によって原因も経過もまちまちです。
薬を飲んでも改善しないことも多く、数値化しづらいものがたくさん含まれています。
つまり、「再現しにくい健康問題」です。
病院での治療が悪いのではなく、エビデンスが届きにくい場所があるということです。
だから、ぬか漬けをうまく作るために、かき混ぜ方を変えたり、塩の量を調整したりして、自分なりに試行錯誤するように、再現しにくい体の不調に対しても、自分に合った方法を探す「仮説と検証」が大切になります。
唐揚げだけを食べて、満足ですか?
ぬか漬けも、ちょっと食べてみたくないですか?
病院で出された薬や治療だけで、体調は万全ですか?
検査の結果は「異常なし」なのに、なんだか調子が悪くはないですか?
ぬか漬けと、エビデンスで説明しきれない不調には、自分自身の手で試してみること、観察すること、変えてみること――そうした、地道な仮説と検証が必要なのです。
エビデンスはたしかに便利です。
それが無かったら、
初めてチャレンジする料理を美味しく作れないし、
病院に行っても、統一ルールが存在せず、
それぞれのお医者さんの勘で治療されてしまいます。
でも、ぬか漬けや病名の付かない体調不良のように
エビデンスだけでは解決しない問題も存在します。
それが、
エビデンスの役割と限界です。
エビデンスの恩恵を受けつつ、
それを絶対視しない。
それが、体調改善を目指す人に
求められる姿勢と言えるのでは、
ないでしょうか?