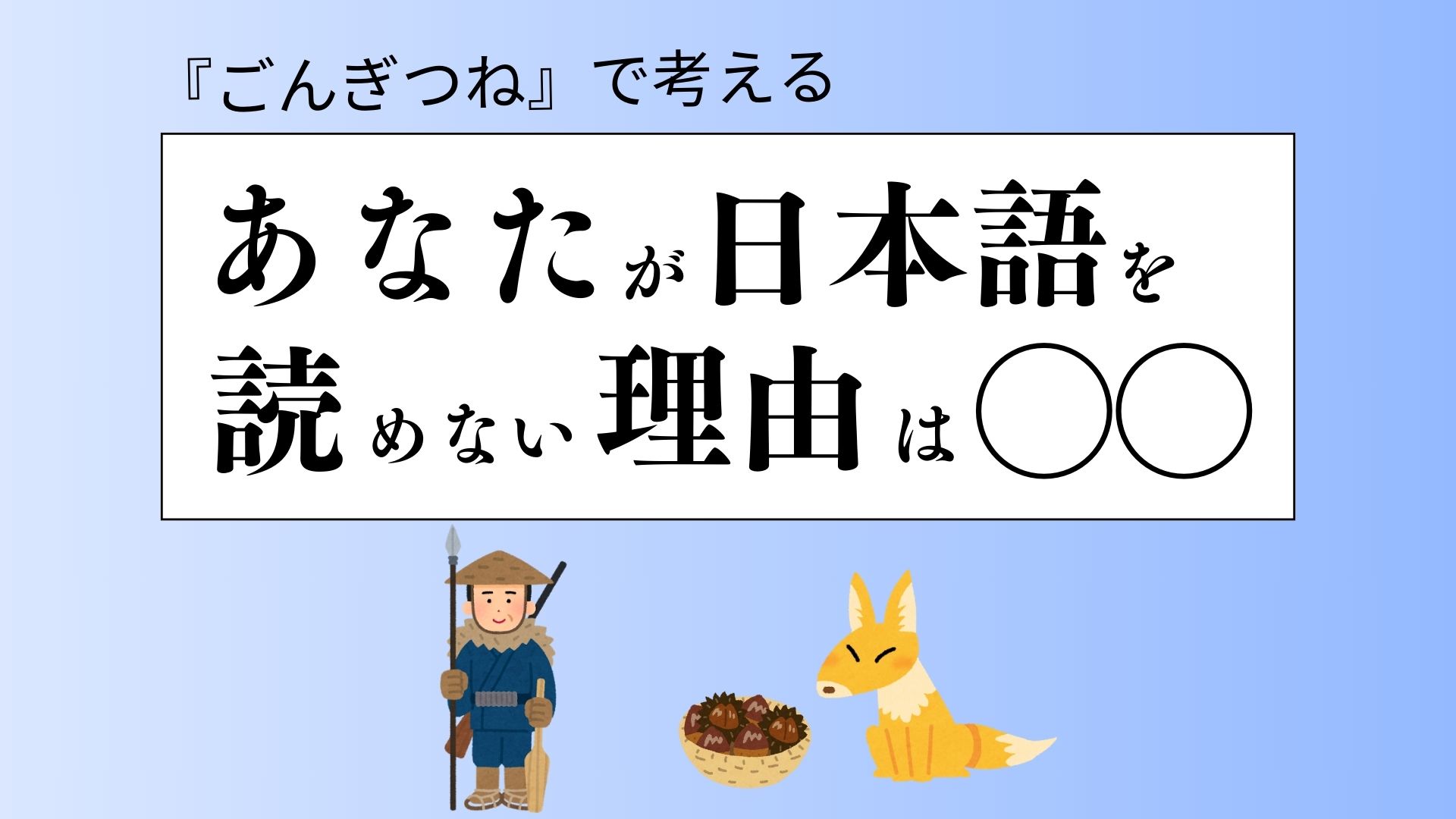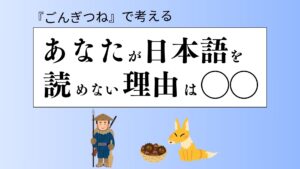第1章 はじめに
日本の国語教育には、他の教科には見られない重大な欠陥がある。
それは、小学校から中学校にかけての国語の授業と、大学受験の現代文の内容が、根本的に異なる能力を要求しているという点だ。
本来、国語という科目は一貫したものであり、初等教育で学んだ読解力がそのまま高校・大学レベルへと発展していくはずである。
しかし、実際には、小学生の国語の授業で求められる読解力と、大学受験の現代文で問われる読解力には、断絶がある。
その最たる例が、「筆者や登場人物の気持ちを答えよ」という設問である。
これは一見、文章の読解力を問う適切な問題のように見えるが、実際には「読解力」とは別の能力を測る問題になっている。
このような問題の出題が常態化していることが、国語教育の本質的な問題点を浮き彫りにしている。
第2章 「ごんぎつね」の問題に見る悪問の本質
「ごんぎつね」は、日本の小学校で広く親しまれている物語であり、国語の授業でも頻繁に取り上げられる。
物語の終盤、主人公のごんは、誤解を解こうとした矢先に兵十に撃たれ、命を落とす。
この場面に対して、「ごんの気持ちを答えなさい」という問題が出されることが多い。
この設問に対して、模範解答とされるのは、「ごんは、突然撃たれて驚いたかもしれない。そして、自分の善意が伝わらなかったことを悲しく思った。しかし、最後に兵十が栗を見たことで、ごんの気持ちが伝わり、安心しただろう」といった内容である。
これは確かに、物語を感傷的に解釈したものとしては妥当かもしれない。
しかし、論理的に考えてみれば、撃たれた直後のごんが「自分の気持ちが伝わったかどうか」などを考えていた可能性は低い。
彼が最後に兵十に頷いて見えたのは、単に彼の体が痙攣した結果として、そう見えただけかもしれない。
さらに、「栗を見て安心した」とするのも、後付けの解釈に過ぎず、実際には痛みと恐怖の中で思考する余裕はなかった可能性が高い。
しかし、このような論理的な考察を行い、「ごんは痛みと恐怖に苦しみ、思考する余裕などなかった」と答えた場合、それは模範解答とは異なるため減点される可能性がある。
つまり、国語の試験では、「論理的な読解力」ではなく、「教師が期待する、子供らしい、感傷的・道徳的な解釈をできるかどうか」が評価される仕組みになっているのだ。
第3章 内側前頭前野の発達と国語の試験
このような試験の問題点は、単なる出題ミスではなく、脳の発達段階を無視していることにある。
読解のプロセスには、主に背外側前頭前野(論理的思考を司る)と内側前頭前野(共感や感情の処理を担う)が関与する。
小学校・中学校の国語の試験では、文章の論理的構造を分析することよりも、「登場人物の気持ちを理解すること」が求められる。
そのため、共感力に優れた生徒、すなわち内側前頭前野の発達が早い生徒 は、試験で高得点を取りやすくなる。一方で、論理的に文章を読もうとする生徒は、評価されにくい。
しかし、大学受験の現代文では、状況が一変する。大学受験の問題では、論理的に文章を整理し、筆者の主張を正しく把握することが求められる。
これは感覚や勘で解けるものではなく、背外側前頭前野を活用して情報を論理的に整理する力が必要になる。
つまり、小学校・中学校で高得点を取れていた「内側前頭前野の早熟タイプ」の生徒が、大学受験では苦戦するケースが多発する。
これは、小中学校の国語の試験が、本来の読解力を測るものではなく、単に「内側前頭前野の早熟な生徒を選別する装置」になっている ことを示している。
第4章 教育ではなく、教員にとっての「省エネ化」
この問題の背景には、国語教育を担当する教員側の事情もある。
論理的に精密な解説を行うことは、非常に高い能力とエネルギーを要する。更に児童や生徒の質問の意図を瞬時に理解して、その論理的な破綻を指摘して、児童が理解できる表現で伝えるというのは、多くの教員とって能力的に不可能である。
しかし、感傷的・道徳的な教育であれば、教師が用意した「模範解答」に沿わせるだけで済み、授業が円滑に進む。
さらに、学習指導要領自体があまりにも抽象的であり、具体的な読解力の育成方法や評価基準が示されていないため、教員自身が読解力をどう育てるべきかを明確に理解できていない。
その結果、「共感的に読めるかどうか」で生徒を選別するという省エネ的な教育 に陥っているのだ。
これは別の言い方をすれば、「子供らしく扱いやすい生徒を選別する作業」であるとも言える。これは子供のためを思った「教育」ではなく、大人側の生活のための「労働」でしかない。
第5章 本来の教育とは何か?
本来、教育とは、「共感しやすく、扱いやすい生徒を選別すること」ではない。
教育とは「すべての生徒が、自分に合った能力を伸ばせる環境を提供すること」である。
国語教育においても、誰しもが適切な手順を踏めば上達できる、論理的な読解力を養成すべきであり、それを評価する方法を確立する必要がある。
教育の目的は、生徒の発達段階や特性に応じて、各自の才能を引き出し、それを社会に還元する喜びを教えることである。
にもかかわらず、現在の国語教育は、教員が扱いやすい回答をする生徒を高評価するだけになってしまっている。
これでは、「教育」ではなく、単なる「管理」に過ぎない。
本来の国語教育を取り戻すためには、まず「読解力を鍛える」とはどういうことか? それをどう評価すべきか?」を明確にする必要がある。
そして、論理的な読解ができる日本人を増やさなくてはならない。それを実現しなければ、自分と考えの違う者と、適切なコミュニケーションが取れず、感情的に対立することだけしかできない大人が、今後も量産され続けることになるだろう。
そして、何かの分野を新しく学ぶ際には、それは多かれ少なかれ、自分とは異なる考えを受け入れるという行為が必要であるが、その際に感情や共感性だけで向かい合おうとすると、『今から学ぼうとする分野を素人考えで評価しようとする』という状態に陥ることがある。
これでは新しい学びが進まないのは明白である。
だから国語教育の欠陥及び、読解力を養成しないまま成人した者の真の恐ろしさは、新たな学びを得ることができないことで、それができる者との間で、知識や経験の格差が生じることであると言える。
そうならないために、読解力を身に着けるためのトレーニングが必要となる。
試しに、こちらのドリルを解いてみて欲しい。
多くの大人は、これが解けないことに愕然とするはずである。
あなたは、内側前頭前野ではなく、背外側前頭前野で文章を読めているだろうか?