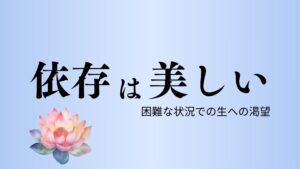何かを決めるとき、誰かの意見がないと不安になる。ひとりで行動するのが怖い。頼ることをやめたいのに、どうしてもやめられない。そんな自分に、嫌気がさしていませんか?
「自分でやらなきゃいけない」と思うのに、どうしても誰かを求めてしまう。「こんなに人に頼ってばかりで、大丈夫なのだろうか」と不安になる。でも、もし頼ることをやめたら、自分は何もできなくなってしまうかもしれない——そんな気がして、結局また依存してしまう。
そんなあなたに、伝えたいことがあります。
あなたが依存するのは、決して弱いからでも、怠けているからでもありません。それは、あなたが「よりよく生きよう」としてきた証です。
もし今、「このままではいけない」「でも、どうしたらいいのかわからない」と感じているなら、まずは立ち止まって、少しだけ考えてみませんか? あなたがこれまで依存してきた理由、そして、それがあなたにとってどんな意味を持っていたのか。この記事は、そんなあなたのためのものです。
どうか、これを読みながら「私は間違っていたのではない」と思えますように。そして、あなたが少しでも楽になれるようなヒントを見つけられますように。
依存が生じる理由——環境がもたらす影響
依存的な態度が生じる背景には、さまざまな環境の影響があります。そのひとつに、思考や行動をするための体力や気力が備わっていないことがあります。心や体が疲れ切っていると、何かを考えて決断し、自ら動くことが難しくなります。そんなとき、人は自然と周囲の人に頼ることでエネルギーを節約しようとします。それは決して怠けではなく、生きるための合理的な選択なのです。
また、過去に「生殺与奪の権利を持つ存在の機嫌を伺わなければならない環境」にいたことも、依存の要因となります。もし幼い頃から、自分の意見を持つことや、自らの判断で行動することが許されず、誰かの顔色を伺って生きることが求められてきたなら、「自分で決めること」は危険なことのように感じられてしまいます。自分の意思を持つことで怒られたり、拒絶されたりする経験を重ねると、やがて「自分の判断ではなく、誰かに決めてもらったほうが安全だ」と学習してしまうのです。それはその場を生き抜くためには必要な適応だったのかもしれません。けれども、大人になって環境が変わった後も、その感覚が続いていると、自分の意志で選択することが怖くなり、他者に依存しやすくなるのです。
さらに、幼少期に「安全な範囲でリスクを取る経験」を積ませてもらえなかったことも、依存的な態度を強める要因のひとつです。たとえば、肉食動物の親は、子どもに狩りを教えるために、最初は弱った獲物を与えたり、簡単な狩りを経験させたりします。これは、突然本番の狩りをさせると、恐怖を覚えて狩りができなくなってしまうからです。人間の成長にも同じことが言えます。小さな失敗を経験し、それを乗り越える機会を与えられることで、人は「挑戦しても大丈夫なんだ」と感じることができます。
でも、もし幼い頃にそうした経験が十分にできなかったなら、それはあなたのせいではありません。もしかすると、あなたを育てた人もまた、適切な難易度の課題を提供する方法を知らなかったのかもしれません。あるいは、余裕がなくて、それどころではなかったのかもしれません。親自身が、自分で決めることに対して恐怖を抱えていたのかもしれません。誰もが、完全に準備された環境で育つわけではありません。もし過去に十分な挑戦の機会がなかったのなら、それは「あなたが怠けたから」ではなく、「あなたが悪かったから」でもありません。ただ、そういう環境だったというだけのことです。
依存は成長の過程であり、悪ではない
依存は、あなたが生き抜くために選んできた手段です。それは、適応であり、自己愛の表現でもあります。人が誰かを頼ることは、決して恥ずべきことではありません。むしろ、それは「信頼する力」を持っている証でもあります。あなたは、誰かを信じることができるからこそ、依存という形でつながりを持とうとしてきたのです。
ただ、もし今「このままでは苦しい」と感じているなら、それは「依存が悪いから」ではなく、「依存の形が今のあなたに合わなくなってきているから」かもしれません。人は環境とともに変わります。過去には必要だった適応が、今のあなたには窮屈に感じられることもあるのです。もしそうなら、少しずつ、新しい適応の仕方を探してみるのもよいかもしれません。
依存から自立へ——少しずつできることを増やしていく
依存を手放すということは、「誰にも頼らないこと」ではありません。むしろ、自分にとって必要な支えを知りつつ、自分でできることを少しずつ増やしていくことです。そのためには、いきなり大きな挑戦をするのではなく、小さな選択を自分でしてみることから始めるといいかもしれません。たとえば、「今日の食事を自分で決める」「何かに迷ったとき、すぐに誰かに相談せず、自分で考える時間を持ってみる」といったことでも十分です。少しずつ、「自分で決めても大丈夫だった」という経験を重ねることで、「自分にはできることがある」という実感が育っていきます。
そして何より、もし依存的な態度を取ることをやめられない自分に苦しさを感じているなら、「これまでずっと、あなたはあなたなりに一生懸命生きてきた」ということを思い出してほしいのです。あなたが依存を選んできたのは、そうすることで生きることができたから。それは決して間違いではありません。ただ、もし今のあなたが「少し変わりたい」と思うなら、その気持ちを大切にしてあげてください。変わることに怖さを感じるのも、当然のことです。でも、その一歩を踏み出すとき、あなたは決して一人ではありません。
依存は、あなたの価値を決めるものではありません。それは、あなたがこれまで生きるために選んできた方法のひとつに過ぎません。そして、あなたは、これからどんな方法を選び取ることもできるのです。焦らなくて大丈夫。あなたのペースで、あなたの未来を選んでいけますように。